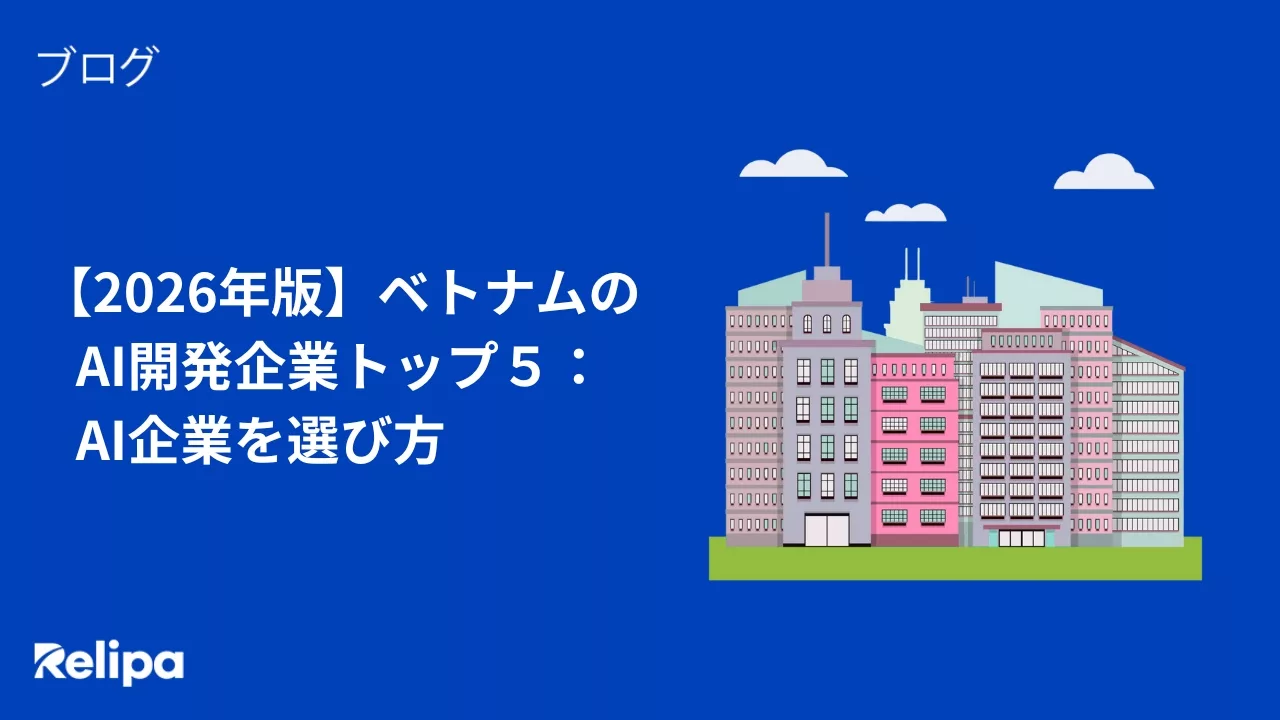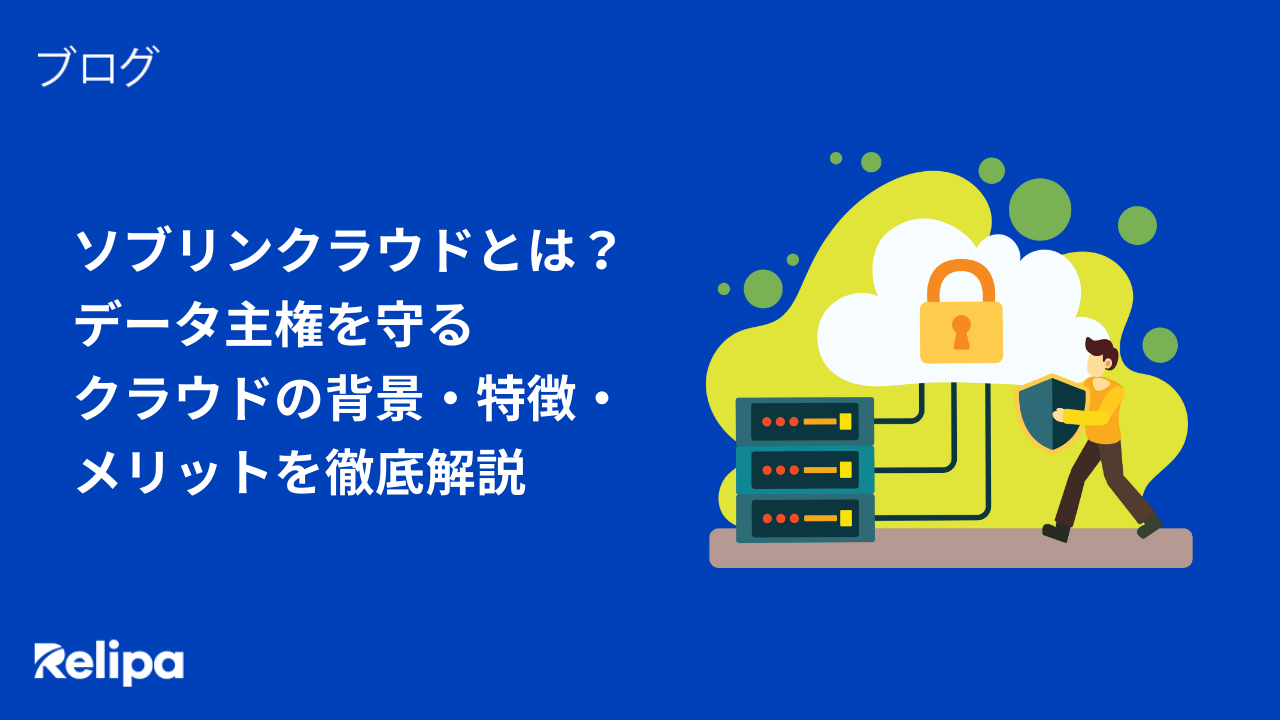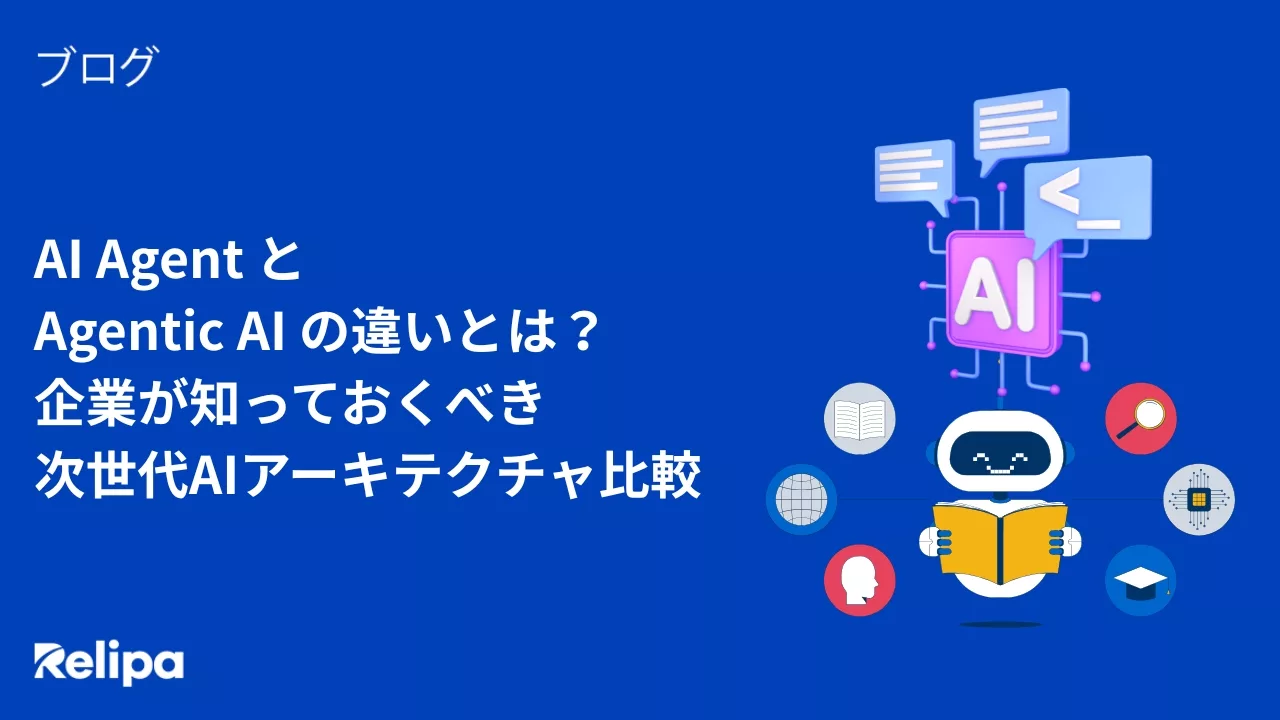「このコード、どこがおかしいですか?」
AIにそう尋ねるだけで、Gitリポジトリを自動解析し、改善案まで提示してくれる時代になりました。
生成AIが急速に普及する中で、外部ツールとの連携は多くの開発現場で課題となっています。
APIごとの個別実装や認証エラー、拡張性の問題などを解決するために登場したのが、MCP(Model Context Protocol)です。
本記事では、以下のポイントを中心にMCPの仕組みと活用方法を分かりやすく解説します。
- MCPの基本概念
- アーキテクチャと主要機能
- 実装手順(Python例付き)
- 日本企業における導入事例
AIとツールをつなぐ新しい標準であるMCPが、今後の開発をどのように変えるのかを一緒に見ていきましょう。
MCP(Model Context Protocol)とは?

MCP(Model Context Protocol)とは、生成AIと外部ツールを標準化された方法で接続するためのオープンプロトコルです。
Anthropic社によって2024年に提唱され、2025年にはClaude、Cursor、Zedなどの主要開発環境が採用しています。
従来、AIと外部システムを連携させる場合は、各サービスのAPIを個別に実装する必要がありました。
そのため、認証方式の違いやエラー処理の煩雑さ、スケーラビリティの限界といった課題が発生していました。
MCPはこれらの課題を解決し、1つの共通プロトコルで複数のツールを安全かつ効率的に接続できる点が最大の特徴です。
まさに、生成AIの世界における「USB-Cのような標準規格」と言える存在です。
例えば、Claude DesktopでMCPを利用すると、AIがGitHubやGoogle Driveなどの外部ツールに安全にアクセスし、ファイル取得・検索・分析といった操作を自動で行うことが可能になります。
これにより、AIの活用範囲が大幅に広がり、業務効率や開発スピードの向上が期待できます。
>>>関連記事:
MCP のアーキテクチャ完全解説
MCP の基本構成
MCP のアーキテクチャはシンプルでありながら拡張性が高く、複数のアプリケーションやサービス間のデータ連携を容易にします。
MCP の基本構成は、主に以下の4つの要素で成り立っています。
- MCP ホスト:
LLM が動作するアプリケーション環境です。Claude Desktop や Cursor、Zed などが代表例で、ユーザーはこのホストを通じて AI に指示を与えます。 - MCP クライアント:
MCP ホスト内に組み込まれ、LLM と MCP サーバーの通信を仲介します。
LLM のリクエストをプロトコルに変換し、サーバーからの応答を LLM が理解できる形式に戻します。 - MCP サーバー:
外部のツールやデータベース、API と接続し、LLM に必要な情報を提供するコンポーネントです。
例として、GitHub、Google Drive、Brave Search などが挙げられます。 - トランスポートレイヤー:
クライアントとサーバー間の通信を管理する層です。
JSON-RPC 2.0 をベースに、標準入出力(stdio)または Server-Sent Events(SSE)を利用してデータを送受信します。
>>>関連記事:
これらのコンポーネントが連携することで、AI は外部データへのアクセスやツールの実行を一貫した方法で行えるようになります。
以下の図は、MCP のアーキテクチャ全体像を示しています。

MCP のデータフロー概要
MCP では、ホスト・クライアント・サーバーの間でデータがどのようにやり取りされるかが明確に定義されています。
これにより、生成AIが外部システムと安全かつ効率的に連携することが可能になります。
処理の流れ(例:Claude が Git リポジトリを解析する場合)
- ユーザーのリクエスト
例:「このコードのどこが問題?」とAIに質問します。 - ホストがリクエストを受信
Claudeなどのホスト環境がLLMを介して、MCPクライアントに処理を依頼します。 - MCPクライアント → MCPサーバー通信
クライアントはリクエストをJSON-RPC形式に変換し、ローカルまたはリモートのMCPサーバーに送信します。 - MCPサーバーがデータを取得
サーバーはGitリポジトリ、ファイルシステム、またはAPIなどの外部リソースにアクセスして必要な情報を取得します。 - 結果の返却と整形
サーバーは結果をクライアントに返し、クライアントがAI(LLM)が理解できる形式に変換します。 - AIが回答を生成
AIが結果を解析し、コード改善案やエラー箇所を提示します。
このように、MCP のデータフローは「ホスト → クライアント → サーバー → 外部リソース → AI応答」という一連の流れで構成されています。
これにより、生成AIは単なる言語モデルにとどまらず、リアルな業務データと連携する知的アシスタントとして機能するのです。
MCP の3大機能
MCP(Model Context Protocol)の中心となるのが、リソース(Resources)、ツール(Tools)、そして プロンプト(Prompts) の3つの主要機能です。

これらの機能によって、AIは単なるテキスト生成モデルから、実行・参照・応答を統合的に行うインテリジェントシステムへと進化します。
リソース(Resources)
リソースは、AIが参照できる外部データを定義する仕組みです。
ファイル、データベース、Gitリポジトリ、ナレッジベースなど、あらゆる情報源をMCPを通して安全にアクセスできます。
例:
- 社内ドキュメントを検索して回答を生成
- GitHub上のコードを解析して改善案を提案
これにより、AIは「学習済み知識」だけでなく「最新の社内データ」を活用できるようになります。
ツール(Tools)
ツールは、AIが外部処理を実行するためのインターフェースです。
MCPでは、ツールが「機能単位」で提供され、LLMはそれらをAPIのように呼び出して動作します。
代表的なツール例:
fetch():外部URLから情報を取得write_file():ローカルファイルを生成・編集brave_search():Web検索を実行
AIがこれらのツールを組み合わせることで、単なる応答生成を超えた「アクションの自動化」が可能になります。
プロンプト(Prompts)
プロンプト機能は、AIの出力を最適化するテンプレートシステムです。
開発者は指示やコンテキストを事前に設定しておくことで、AIの回答精度と一貫性を高めることができます。
利用例:
- 特定のフォーマットでコードレビューを行う
- 一定のトーンや文体でレポートを生成
これにより、AIは「状況に応じた適切な出力」を自動的に行うことができます。
MCPの3大機能は、それぞれ独立していながら密接に連携しています。
- リソース → データを提供
- ツール → 処理を実行
- プロンプト → 応答を最適化
この構成によって、AIはリアルタイムで外部情報にアクセスし、より実用的なタスクを安全に遂行できるようになります。
>>>関連記事:
MCPと生成AIの統合ポイント
AI MCPとは
「AI MCP」とは、MCPを実装した生成AI環境のことを指します。
Claude、GPT、GeminiなどのLLMがMCPクライアントを通して外部ツールと連携することで、以下のような動作が可能になります。
例:
- 「このPull Requestをレビューして」と指示すると、AIが自動でGitHubからコードを取得・分析
- 「社内レポートを要約して」と言えば、DriveやNotionのデータを参照して要約を生成
つまり、AI MCPはLLM + MCP + 外部リソースという構成で、実際の業務タスクを自動化します。
従来方式との違い
従来のAIツール連携では、各APIに個別の実装が必要でした。
これに対してMCPは、共通プロトコル(JSON-RPC 2.0)でツールやデータを扱うため、開発・保守の負担を大幅に削減します。
| 比較項目 | 従来方式 | MCP方式 |
|---|---|---|
| 連携方法 | APIごとの個別実装 | 標準化されたプロトコル |
| 認証処理 | 各サービスで異なる | 共通形式で統一 |
| スケーラビリティ | サービス追加ごとに拡張必要 | 1つのMCPで多数ツール対応 |
この仕組みは、生成AI界における「USB-C」的標準化とも言えます。
A2Aとの関係
MCPは主に「AI ↔ ツール」を接続するのに対し、A2A(Agent-to-Agent)は「AI ↔ AI」を連携させるプロトコルです。
今後は、MCPでツールを操作しながら、A2Aで複数のエージェントが協働するハイブリッド環境が一般化すると予想されています。
| 対象 | 使用プロトコル | 主な用途 |
|---|---|---|
| MCP | JSON-RPC | AIとツールの連携 |
| A2A | gRPC | AI同士の協調動作 |
MCPは、生成AIが現実世界のシステムやデータと安全に結びつくための基盤技術です。
企業がAIエージェントを本格導入するためには、MCPを理解し、どのように既存システムと統合するかを設計することが重要になります。
MCP の実装方法
環境の準備
まず、MCPを利用するAIアプリケーションまたは開発環境を用意します。代表的な対応環境には、Claude Desktop、Cursor、Zed などがあります。
Pythonで独自に実装する場合は、次のライブラリをインストールします。
pip install jsonrpcserver requests
これらのライブラリを利用することで、MCPクライアントとサーバー間の通信をJSON-RPC 2.0 プロトコルで安全かつ効率的に行うことができます。
MCPサーバーの構築
MCPサーバーは、実際に外部リソース(データベースやAPIなど)にアクセスし、AIが要求するデータを返す役割を持ちます。
以下はPythonで実装した簡易的なサーバー例です。
# mcp_server.py
from aiohttp import web
from jsonrpcserver import method, async_dispatch
@method
async def get_user_data(user_id):
return {"user_id": user_id, "name": "Taro", "role": "Engineer"}
async def handle(request):
request_json = await request.text()
response = await async_dispatch(request_json)
if response.wanted:
return web.json_response(response.deserialized())
return web.Response()
app = web.Application()
app.router.add_post("/", handle)
if __name__ == "__main__":
print(" MCP Server running on http://localhost:8000 ...")
web.run_app(app, host="localhost", port=8000)
このサーバーでは、get_user_data() メソッドがAIからのリクエストを受け取り、指定されたユーザー情報をJSON形式で返します。
MCPクライアントの設定
次に、AIまたはアプリケーション側からMCPサーバーへリクエストを送信するクライアントを設定します。
# mcp_client.py
import requests
import json
SERVER_URL = "http://localhost:8000"
payload = {
"jsonrpc": "2.0",
"method": "get_user_data",
"params": {"user_id": 123},
"id": 1
}
response = requests.post(SERVER_URL, json=payload)
print(json.dumps(response.json(), indent=2, ensure_ascii=False))
このコードでは、クライアントがget_user_dataメソッドを呼び出し、サーバーが結果を返します。実行すると、以下のような出力が得られます。
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"user_id": 123,
"name": "Taro",
"role": "Engineer"
},
"id": 1
}
実行手順まとめ
- 依存ライブラリをインストール
mcp_server.pyを起動(サーバー側)mcp_client.pyを実行(クライアント側)- クライアントがサーバーにリクエストを送り、JSONで結果を受け取る
MCPの実装は、JSON-RPCによる標準化された通信を採用することで、LLMと外部システムの連携を簡単かつ安全に実現します。
このような仕組みを導入することで、生成AIは単なる対話エンジンから、現実の業務データやシステムを自在に操作する「実行可能エージェント」へと進化します。
MCPの活用事例
海外では、多様な分野・サービスでMCPの導入が進んでおり、企業の業務効率化や自動化を大きく後押ししています。ここでは、代表的な活用事例をいくつか紹介します。
社内システムとの統合による業務自動化
企業独自の社内システムをMCP経由でAIモデルと連携させることで、知識の検索や社内データの活用が容易になります。Block社やApollo社のように、既存システムをAI対応にすることで、ドキュメント生成やタスク自動処理などが実現しています。
コミュニケーションツールでの情報整理
Slackでは公式のMCPサーバーが提供されており、チャンネルを横断した会話の要約や議事録の自動生成などが可能です。これにより、情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム全体のコミュニケーション効率を向上させます。
スケジュール調整の自動化
GoogleカレンダーやGoogle MeetのMCP連携を活用すれば、AIが自動的に空き時間を確認し、会議予定やMeetリンクを作成します。これまで煩雑だったスケジュール調整が、わずか数秒で完了します。
データ分析の民主化
BigQueryのMCPサーバーを利用することで、非エンジニアでも自然言語でデータ分析を行うことができます。チャットベースでクエリを実行し、広告パフォーマンスや顧客データの傾向を簡単に把握できるようになります。
AIによるリサーチ業務の高度化
TavilyやBrave Searchなどの検索系MCPを導入すれば、AIがウェブ検索を行い、情報を要約・比較・整理して提示します。口コミ収集や競合調査などにも応用可能です。
画像生成・編集の自動化
Stability AIのMCPサーバーを利用すれば、ClaudeなどのAIツールから直接画像生成や背景削除が実行できます。デザイン作業の初期段階を自動化し、クリエイティブ業務のスピードを大幅に向上させます。
数値計算や数理分析の強化
WolframAlphaとの連携により、AIが苦手とする数式処理や定量分析を補完できます。理論検証やデータ分析など、研究開発分野でも活用が進んでいます。
マルチLLM運用による作業継続性の確保
DeepSeekのMCPサーバーを利用すると、チャット上限を超えても履歴や設定を保持したまま別のLLMに引き継ぐことが可能です。長時間の作業やプロジェクトベースのAI活用に最適な仕組みといえます。
開発プロセスの自動化
GitHubのMCPサーバーでは、コードの管理・テスト・デプロイまでをAIが自動化します。Slackやタスク管理ツールと組み合わせれば、開発チームの生産性をさらに高められます。
ファイル管理とナレッジ共有の効率化
GoogleドライブのMCPサーバーを利用すると、保存されたドキュメントの検索・要約・共有が自然言語で可能になります。社内のナレッジ共有やレポート作成に非常に有効です。
これらの事例からわかるように、MCPは単なる技術仕様ではなく、「生成AIをビジネスシーンで最大限活かすための基盤」として機能しています。
各種ツールやデータベースをMCPでつなぐことで、AIはより実務的なタスクをこなす「エージェント」へと進化します。今後、企業のデジタル変革(DX)やAI導入戦略において、MCPの重要性はますます高まっていくでしょう。
MCP の今後の展望
MCP(Model Context Protocol)は、生成AIと外部システムをつなぐ「共通言語」として、今後さらに発展していくことが期待されています。現在はClaudeやGemini、GPTなど一部のLLM環境での実装が進んでいますが、将来的にはより多くのAIプラットフォームがMCPを採用し、エコシステム全体が拡張されていく見込みです。
まず注目されるのは、AIエージェント間の相互運用性の向上です。これまでは、各AIが独自のAPIやプラグインを通じて限定的に連携していましたが、MCPの普及により、異なるAI間でデータや機能を安全にやり取りできるようになります。たとえば、Claudeが生成した文章をGPTが自動的に翻訳し、Geminiが可視化するような、シームレスなワークフローが実現するでしょう。
次に、企業向けのカスタムMCPサーバーの拡大も大きなトレンドです。自社データベース、ERP、CRMなどの業務システムをMCPでAIとつなぐことで、より高度な業務自動化や知識活用が可能になります。特にセキュリティやガバナンスを重視する日本企業にとって、MCPは「安全にAIを導入するための標準仕様」としての役割を担う可能性があります。
さらに、オープンソースコミュニティの貢献もMCPの発展を後押ししています。多様な開発者がMCPサーバーやツールキットを公開することで、個人開発者でも手軽にAIアプリを拡張できる時代が到来しています。こうした動きは、AI技術の民主化にも大きく寄与するでしょう。
今後、MCPは「AIが人間の代わりに行動する」ための重要なインフラとして進化していくと考えられます。
単なるAPI連携の枠を超え、企業・開発者・AIプラットフォームが共有できる新しいAIエコシステムの基盤として、MCPはこれからの数年でさらに存在感を高めていくでしょう。
まとめ
MCP(Model Context Protocol)は、生成AIを単なる情報生成ツールから実務で活かせるAIエージェントへと進化させる基盤として、今後ますます重要性を増していきます。社内システムやクラウドサービス、データベースとの連携を通じて、業務効率化、情報共有、意思決定の高度化を実現できるだけでなく、企業は安全かつ柔軟にAIを導入することが可能です。
導入事例からも明らかなように、MCPは多様な業務シーンで活用でき、その可能性は発想次第で無限大です。今後、AIエージェント間の相互運用性向上やカスタムMCPサーバーの拡充により、さらに多くの企業がMCPの恩恵を受けられるでしょう。
もし、MCPを活用したAI導入や業務自動化に関心がある場合は、経験豊富なRelipaのチームにご相談ください。
Relipaは9年以上にわたるWeb3・AI・ブロックチェーン開発実績を持ち、BrSEや日本語対応可能な技術者を擁しています。企業ニーズに合わせたMCP導入・運用支援を提供し、貴社のAI活用を最短距離で実現します。



 EN
EN